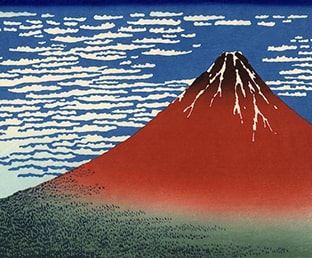はじめに
日本の美術史に大きな足跡を残した上村松園(うえむら しょうえん)をご存知でしょうか。明治から昭和という激動の時代に、女性の美しさと強さを描き続け、女性として初めて文化勲章を受章したこの画家の作品は、今日でも高い評価を受け続けています。また小倉遊亀、片岡球子と並び「日本三大女流画家」とも呼ばれています。
本記事では、美人画の最高峰として名高い上村松園の魅力をご紹介します。作品の価値や買取に関する情報も含めてご説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

上村松園とは?
女性初の文化勲章受章者としての功績
1875年、京都の下京区四条通御幸町にある葉茶屋「ちきり屋」で、上村松園は次女として生まれました。本名を津禰(つね)という松園は、生まれる2か月前に父親を亡くしています。
松園の芸術の原点となったのは、母・仲子の存在でした。女手一つで松園と姉を育て上げた母は、当時の女性が画家を志すことが認められない時代にあっても、常に松園を理解し、励まし、支え続けました。
松園は著書『青眉抄』で「私は母のおかげで、生活の苦労を感じずに絵を生命とも杖ともして、それと闘えたのであった。私を生んだ母は、私の芸術までも生んでくれたのである」と母への深い感謝を述べています。母を亡くした後には、「母子」「青眉」「夕暮」などの格調高い追慕の作品が生まれました。
幼い頃から絵を描くことが好きだった松園は、ちきり屋に出入りする文人たちの間でも、その才能が話題となるほどでした。
母の後押しもあり、12歳で京都府画学校(現:京都市立芸術大学)に入学。そこで人物画を得意とする鈴木松年(すずきしょうねん)に師事しましたが、翌年の松年の退職に伴い学校を退学し、松年塾へと進みます。
松園の随筆によれば、「松園」という号は、師の「松」という一字と、実家の葉茶屋にゆかりのある「園」を組み合わせたものとされています。
そして15歳のとき、松園の人生を大きく変える出来事が起こります。第三回内国勧業博覧会に出品した「四季美人図」が、見事一等褒状を受賞したのです。
さらにこの作品は、当時来日していた英国皇太子コンノート殿下の目に留まり、買い上げられることになり、「京に天才少女有り」という評判が、たちまち世間に広がっていきました。
3人の師から学んだ画業の深化
芸術家としての道を歩み始めた松園は、さらなる高みを目指します。鈴木松年の後、幸野楳嶺(こうのばいれい)に師事し、そして楳嶺の死後は竹内栖鳳(たけうちせいほう)の門下となりました。
この3人の師から学んだ四条派の技法と新たな画法は、後の松園独自の画風を形作る重要な要素となったのです。
京都という日本の伝統文化の中心地で育った松園は、「真・善・美の極致に達した本格的な美人画」という理想を追い求め続けました。その真摯な姿勢と卓越した技術は、やがて大きな実を結びます。
1948年、ついに女性として初めての文化勲章受章という栄誉を手にしたのです。現代の画壇では「松園の前に松園なく、松園の後に松園なし」と評されるほどの、比類なき画家となりました。

上村松園の作品の魅力や特徴
上村松園の美人画の真価
松園の作品の最大の魅力をご存知でしょうか。
それは、女性の優美さを描きながらも、毅然とした品格を表現できる、唯一無二の画力にあります。
松園自身は「一点の卑俗なところもなく、清澄な感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願とするところのものである」と語っています。
その言葉通り、女性の内面の美しさや清らかさが感じられる作品を生み出し続けました。
独自の技法と表現方法
松園の画技は、四条派の影響が色濃く表れています。
一方で、彼女の大きな特徴として特筆すべきは、すべての作品を毛筆のみで描いたという点です。繊細な細い線と力強い太い線を自在に操り、独特の表現を生み出しました。また、抑制の効いた色彩使いと無駄のない構図で、凛として気品溢れる女性像を確立させていったのです。
京都の伝統文化に囲まれて育った松園は、写実的な手法を用いながらも、単なる写実を超えた表現を目指しました。
その追求は、対象の外見的な美しさだけでなく、女性の内面に潜む心理の描写にまで及びます。特に日本髪のリアリティやぼかし技法を駆使した生え際の表現には定評がありました。
さらに松園の作品では、細部への徹底的なこだわりが特徴となっています。例えば、重要文化財「序の舞」では、朱色と鶯色が映える振袖姿に、丹念に描かれた総絞りの帯揚げ、精緻な菊柄の半襟など、細部にわたる描写の一つ一つに品格が漂っているのです。
また、浮世絵のような構図で、胸から上を画面いっぱいに描いた大首絵も、松園作品の特徴として広く知られています。
このような緻密な技法と表現は、松園が古典を学ぶべく描いた膨大な量の縮図(古名画の模写)の経験が基礎となっています。
また、能楽を学び、日本の美の神髄を極めようとした姿勢も、その作品の気品の高さに大きく影響しているといえるでしょう。
代表的な作品とその評価
松園の代表作をご紹介します。まず特筆すべきは、重要文化財に指定された「母子」(1934年)と「序の舞」(1936年)です。
母子

「母子」は、松園にとって永遠のテーマである母への思いを描いた作品です。
精神的支えとなっていた母への追悼の思いを込めて1934年に制作され、第15回帝展に出品されました。松園にとって母親は、自身を支え続けてくれた存在であるとともに、芸術の源泉でもありました。
「私を生んだ母は、私の芸術までも生んでくれたのである」という松園の言葉からも、この作品に込められた深い愛情と敬愛の念が伝わってきます。
序の舞

「序の舞」は、松園61歳の時に完成させた畢生の作品です。
楚々としたお嬢様が鮮やかな赤を基調とした振袖に身を包み、扇を手にして日本舞踊を舞う姿が格調高く描かれています。優雅に「序の舞」を舞う令嬢の姿には、松園が追い求めた理想の女性像が表現されています。
興味深いことに、このモデルは松園の息子・松篁の妻である「たね子」です。この絵のために、京都で一番の結髪師に文金高島田(ぶんきんたかしまだ)を結ってもらい、嫁入りの時の大振袖を着せたといいます。
焔

出典:Wikipedia
異色の作品として知られる「焔」(1918年)もご存知でしょうか。源氏物語の六条御息所をモデルとしたこの作品では、髪の端を噛んで振り返る姿で生霊と化した女性を表現しています。
普段の気品ある美人画や母性溢れる作品とは一線を画す異色作として、女性ならではの激しい感情表現が高い評価を受けています。
収蔵先となる主要美術館
では、実際に松園の作品はどこで見ることができるのかご紹介します。
東京国立博物館、東京国立近代美術館、京都市京セラ美術館など、日本を代表する美術館が松園の作品を所蔵しています。
特に「序の舞」は東京藝術大学に、「母子」は東京国立近代美術館に収蔵されており、定期的に公開されています。
上村松園作品の買取相場・実績
※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。
◆重要文化財に「母子」の作品があり、母子を描いた人物画や美人画の作品は⾼価買取の対象で100〜300万円といった価格帯での査定が期待できます。
なかでも母子像や、着物や背景の細部まで描き込まれているような代表作は1,000万円を超える査定になることもあります。
春雨

「一点の卑俗なところもなく、清澄な感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願とするところのものである」と生前に語り、近代美人画としての立場を確立し女性として初めて文化勲章を受章しました
円窓美人

江戸期の髷の美人。あえて背景や周りを描かず、中央に配置せず計算され構成された作品です。
白拍子

白拍子は平安朝末から始まった歌舞の一種で、主に男装の遊女や子供が今様や朗詠を歌いながら舞ったものを指すが、男性の白拍子もいました。松園は若い頃より古典芸能にも関心を抱き制作に反映しました。
上村松園作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。
上村松園の作品を高値で売却するポイント

上村松園の鑑定機関・鑑定人
- 東美鑑定評価機構 鑑定委員会
一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。
来歴や付帯品・保証書
来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。
保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。
贋作について
ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。
ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。
落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。
日本画(額)
状態を良好に保つ為の保管方法
日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう
修復方法
日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります
共シール
「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。
掛軸
状態を良好に保つ為の保管方法
掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。
共箱(ともばこ)
掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。
書付、識箱・極箱
“共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。
書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。
識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。 ”
水彩・デッサン
主に紙に描かれていることの多い水彩やデッサンは、モチーフに対して紙の余白がある反面、しみや日焼けが目立つ事があります。
版画
共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)
版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。
主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。
リトグラフ
石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。
木版画
板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。
シルクスクリーン
枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。
上村松園についての補足情報

近年の展覧会情報と市場評価
松園の作品は、現代でも新たな発見が続いているのをご存知でしょうか。
2021年には、長年行方不明だった「清少納言」が名古屋市内の画廊経営者によって発見されました。
制作当時の美術雑誌や松園の随筆との照合により、松園自筆の本物と確認された「清少納言」は、約100年の空白期間を経て回顧展で公開され、大きな話題を呼びました。
この作品では、清少納言の美しい黒髪の表現や、簾越しに広がる雪景色の描写に、松園独特の優美な筆遣いを感じ取ることができ、展覧会は大盛況となりました。各地の美術館でも定期的に展覧会が開催され、その人気は今なお衰えることを知りません。
ニュース記事:上村松園の日本画、100年ぶり発見 京都で初公開
画壇における松園の影響力と評価
松園の芸術は、次世代へと確実に受け継がれています。子の上村松篁、孫の上村淳之という3代にわたる日本画家の家系を築いただけでなく、松園の死後には若手女流日本画家を対象とした「上村松園賞」が設けられました。
秋野不矩・小倉遊亀といった「上村松園賞」の受賞者たちは、後に松園と同じく文化勲章を受章し、日本美術史において大きな功績を残しています。
まとめ
毛筆一本で女性の優美さと凛とした強さを描き続けた上村松園。その作品群は、日本美術史に大きな足跡を残すとともに、現代の美術品市場でも高い評価を得ています。
2021年には100年間行方不明だった作品「清少納言」が発見され大きな話題となるなど、松園作品への関心は今なお衰えることを知りません。
作品をお持ちの方は、ぜひ一度専門家による査定をご検討ください。松園芸術の真価を見極め、適切な評価をさせていただきます。
当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。上村松園の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。
また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。