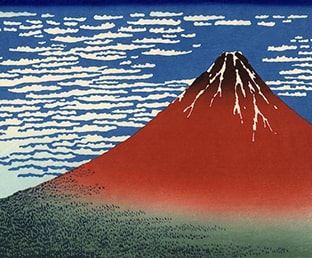はじめに
「猿の関雪」と称された天才画家・橋本関雪(はしもと かんせつ)。その名前からは「新南画」や動物画の名手というイメージが連想されるのではないでしょうか。
橋本関雪は、中国南画の伝統に近代的感覚を取り入れた「新南画」で名声を博し、晩年は動物画、特に猿の描写で卓越した技術を見せた日本画家です。儒学者の父から受け継いだ漢学の素養と四条派で培った写実技法を融合させ、独自の芸術世界を確立していきました。
今回は、そんな橋本関雪の生涯と作品の魅力をご紹介します。作品の価値や特徴についても解説しておりますので、橋本関雪作品をお持ちの方、売却をご検討の方はぜひ最後までお読みください。

橋本関雪とは?
漢学の教養と日本画の技を極めた画家の生涯
橋本関雪は1883年に兵庫県神戸市で誕生しました。幼い頃は成常と呼ばれ、青年期には本名である関一(貫一)を名乗りました。「関雪」という画号は、明石藩で儒学者として知られた父・海関によって名付けられたもので、藤原兼家が雪降る逢坂の関を越える夢を見たという故事に由来します。
幼少期から父の薫陶により漢詩や書画に親しんだ関雪は、12歳で四条派(※)の画家・片岡公曠に入門し、17歳で本格的に画家の道を歩み始めました。
1903年、関雪は京都画壇の重鎮であり近代日本画の先駆者として知られる竹内栖鳳が主宰する画塾「竹杖会」に参加します。日露戦争への従軍があったため栖鳳の指導を受けたのは実質的には1年半程度でしたが、この期間に日本画の基礎を身につけ、芸術家としての才能を花開かせていきました。
竹杖会では上村松園をはじめとする多くの新進気鋭の日本画家との交流がありましたが、のちに門を離れた関雪は独自の道を模索することになります。
関雪の芸術は、儒学者だった父親から受け継いだ中国文化への深い造詣と東洋古美術への研究が基盤となっています。幼い頃から培われた漢学の知識は、後の芸術活動において大きな影響力を持つこととなりました。あなたは伝統と革新が融合したこのような日本画家の作品世界に触れたことがありますか?
※四条派:京都を中心に発展した日本画の流派。18世紀後半に円山応挙が始めた写実的な画風を継承し、自然や動植物を精緻に描写することを特徴とする。

文展・帝展での栄光と芸術家としての成長
橋本関雪の画壇デビューは、1908年の第2回文展(※)で初めて作品が入選したことから始まります。その後、1913年と1914年の文展では二等賞を獲得し、芸術家としての地位を着実に固めていきました。続く1916年と1917年の文展では連続で特選を受賞し、日本画界における重要な存在として認められるようになります。
生涯で30回を超える中国訪問を重ねた関雪は、漢詩の世界観を取り入れた作品を意欲的に発表し続けました。この時期に確立された「新南画」(※)と呼ばれる画風は、中国の伝統的な文人画に現代的な感性を取り入れた新しい表現として高い評価を受けました。
後期印象派の影響も受けながら、ただ対象を描写するだけでなく、自身の内面世界を表現する作品を追求したのです。関雪は東西の美術に広く関心を持ち、ヨーロッパへの旅行を通じて西洋美術からも影響を受けましたが、同時に自身の芸術的アイデンティティが東洋にあることを再認識する機会ともなりました。
文展と帝展(※)の審査員を歴任し、1934年には帝室技芸員の称号を得た関雪は、日本画壇の中心的存在として活躍し続けました。1945年2月に61歳で亡くなるまで、多様なジャンルの作品創作に情熱を注ぎ、日本美術史に深い足跡を残したのです。
※文展:文部省美術展覧会の略称。1907年から1918年まで開催された国主催の美術展覧会。
※新南画:中国南画(文人画)の伝統に近代的感覚を取り入れた新しい絵画表現。
※帝展:帝国美術院展覧会の略称。1919年から1934年まで開催された国主催の美術展覧会で、文展の後継にあたる。
橋本関雪の作品の魅力や特徴
技法と表現から見る橋本関雪の芸術性
橋本関雪の作品を特徴づける最も重要な要素は、四条派の写実的技法と南画(※)の精神性を融合させた独自の表現方法にあります。関雪は「絵画とは単なる物体の描写ではなく、画家が想像力を駆使して内面世界を表現するもの」という芸術観を持っていました。この理念に基づき、四条派で培った写実技術に加え、繊細さと妖艶さを併せ持つ独特の筆遣いで作品を生み出していったのです。
関雪作品のもう一つの特徴は、背景を簡素化し余白を効果的に活用する表現技法です。特に動物画においてこの手法が顕著に見られ、描かれる動物の存在感を一層引き立てる効果を生んでいます。また、墨の濃淡の微妙な変化だけで動物の毛並みの質感を表現するなど、緻密な観察眼と卓越した描写力も関雪作品の大きな魅力となっています。
東洋の伝統的画法を深く研究しながらも新たな解釈を加えた関雪の芸術は「新古典主義」(※)と分類されることがあります。中国を30回以上訪問し、その文化や古美術を徹底的に学んだ関雪は、表面的な美しさだけでなく、内面の深い精神性を表現した独自の画風を確立しました。このような関雪のアプローチは、当時の美術界に新鮮な視点をもたらしたのです。
※南画:中国の南宋時代に発展し、日本にも伝わった文人画の一種。墨の濃淡を活かした水墨画が中心で、画家の教養や精神性を重視する。
※新古典主義:伝統的な古典様式を基盤としながら新しい解釈や表現を加えた芸術様式。

橋本関雪の代表作品とその魅力
橋本関雪の代表作として広く知られているのが「玄猿」です。1933年に制作されたこの作品は、昭和天皇から高い評価を受け、文部省に買い上げられた傑作です。この作品により関雪は「猿の関雪」と呼ばれるようになりました。
墨の微妙な濃淡だけで黒テナガザルの柔らかな毛並みを表現し、伸ばされた手の動きには生命力が宿っています。「玄猿」という題名には「天の猿」という意味が込められており、亡き妻・ヨネを偲ぶ追悼の思いを込めて描かれたとされています。
「琵琶行」は唐の詩人・白楽天の詩に着想を得た作品で、政争に敗れて左遷された白楽天が湖畔で琵琶を奏でる女性と出会う場面を描いています。女性の優美な姿と作品全体から感じられる哀愁が見事に表現されています。
「木蘭」は中国の伝説的人物である木蘭(もくらん)を題材にした作品です。木蘭はディズニー映画「ムーラン」のモデルともなった人物で、老いた父の代わりに男装して戦場に赴いた勇敢な女性です。関雪の作品では、戦地から帰途についた木蘭が、長らく隠していた女性としての姿を取り戻す瞬間が表現されています。


出典:白沙村荘 橋本関雪記念館
橋本関雪作品に見る時代ごとの変遷
橋本関雪の画業は多岐にわたり、生涯を通じて様々な主題と表現を探求しました。画家としての初期には「静御前」「聖徳太子」といった日本的題材を選んでいましたが、この時期の作品は画壇での評価を得るには至りませんでした。
関雪が芸術家として認められるようになったのは、大正期に「新南画」と呼ばれるスタイルを確立してからです。父から学んだ漢詩の知識と中国文化への理解を基礎に、独自の絵画世界を開拓していきました。
昭和期に入り50代を過ぎた頃から、関雪はそれまでとは大きく異なる写実的な動物画の制作に力を入れるようになります。「猿の関雪」と称されるほど猿を題材にした作品を多く残しましたが、その動物画の対象は多様でした。大正時代には馬を多く描いたことから「馬の関雪」とも呼ばれており、晩年には国家のために戦争画も手がけています。
このように時代によって変化を見せた橋本関雪の作品ですが、一貫して東洋的精神性と高度な技術が融合した独自の世界観を保ち続けていました。その多彩な表現力と深い教養に裏打ちされた作品群は、現代においても多くの人々を魅了し続けているのです。

橋本関雪作品の買取相場・実績
※下記では、過去に実際に当社で取り扱った橋本関雪の作品をご紹介いたします。
当社では、これまでに橋本関雪作品を多数取り扱っており、豊富な査定・買取実績がございます。作品の評価や真贋のご相談など、お気軽にご相談ください。



橋本関雪の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。
橋本関雪の作品を高値で売却するポイント

橋本関雪の鑑定機関・鑑定人
- 東美鑑定評価機構 鑑定委員会
一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。
来歴や付帯品・保証書
来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。
保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。
贋作について
ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。
ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。
落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。
日本画(額)
状態を良好に保つ為の保管方法
日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう
修復方法
日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります
共シール
「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。
掛軸
状態を良好に保つ為の保管方法
掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。
共箱(ともばこ)
掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。
書付、識箱・極箱
共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。
書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。
識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。
版画
共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)
版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。
主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。
リトグラフ
石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。
木版画
板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。
シルクスクリーン
枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。
橋本関雪についての補足情報
橋本関雪の芸術活動と白沙村荘

橋本関雪は絵画だけでなく作庭の分野でも高い評価を受けています。1916年には関雪の邸宅「白沙村荘」が完成しました。京都の銀閣寺前に広がる約一万平方メートルの広大な敷地には、3つのアトリエと茶室が設けられ、敷地の約7割を占める庭園が配されています。
関雪は「庭を造ることと絵を描くことは本質的に同じである」という考えを持ち、庭園においても中国からの影響と独自の美意識を融合させた独特の空間を創出しました。現在、白沙村荘は橋本関雪記念館として公開されており、2003年には国の名勝に指定されています。
白沙村荘以外にも、関雪は兵庫県明石に「蟹紅鱸白荘」、滋賀県大津に「走井居」、兵庫県宝塚に「冬花庵」を造営しました。これらの庭園はいずれも伝統的手法を基盤としながらも新たな要素を取り入れた独創的なものとなっています。
最近の橋本関雪評価と美術市場での動向
2023年は橋本関雪の生誕140周年にあたる記念の年でした。この機会に関雪の芸術を紹介する大規模展が京都市内の3館で同時開催され、多くの優れた作品が一堂に会しました。
現代においても橋本関雪の作品は高い人気を保ち、美術市場で価値ある作品として取引されています。作品の内容や状態によっては数十万円で取引されるものもあり、代表的な作品では数千万円の価値を持つものも存在します。
もしお手元に橋本関雪の作品をお持ちの方は、その価値を正確に知るためにも、専門の鑑定士による査定を受けてみてはいかがでしょうか。
まとめ
中国文化と日本画の伝統を融合させた橋本関雪。その作品は「新南画」の精神を体現し、後に「猿の関雪」と称されるほどの動物画の名手として広く認知されました。
四条派の写実性と漢詩世界の深い理解から生まれた関雪の作品は、美術館に展示されるだけでなく、今なお美術市場で高い評価を受け続けています。
当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。橋本関雪の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。
また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。