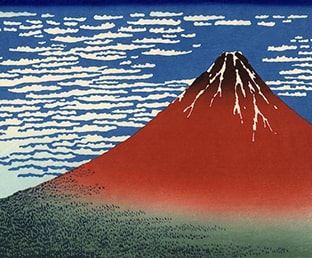はじめに
フレスコ画*と日本の仏画を融合させた独特の表現技法で知られる有元利夫(ありもと としお)。わずか10年という活動期間で371点のタブローと130点の版画作品を残し、38歳という若さでこの世を去った画家です。
神秘的な人物像と幻想的な世界観で描かれた有元利夫の作品は、いずれも希少性が高く、美術品市場でも高い評価を受けています。特に油彩作品は数百万円から1000万円以上の価値を持つものもあり、日本人作家の中でも屈指の評価を得ています。
本記事では、フレスコ画に魅せられ、独自の表現技法を確立していった有元利夫の軌跡と作品の特徴、そして作品の価値についてご紹介します。作品の買取に関する情報もご用意していますので、有元利夫の作品をお持ちの方、売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。
※フレスコ画:漆喰が乾かないうちに水で溶いた顔料で描く壁画技法。「フレスコ」はイタリア語で「新鮮な」という意味。漆喰と顔料が化学反応を起こして固まるため、耐久性が高く、何世紀も色彩を保つことができる特徴を持つ。

有元利夫とは?
天才画家としての軌跡
「この作品は何だろう」と見る人に想像させ、物語を紡がせる絵を描きたい—。そんな思いを抱き続けた画家が有元利夫です。1946年、疎開先の岡山県津山市で生まれた有元は、生後まもなく東京の谷中に戻り。暮らし始めました。
幼少期から絵画への強い関心を示した有元は、特にゴッホの作品に魅了されていたといいます。その才能は周囲からも認められ、小学生の時には絵画コンクールで最優秀賞を受賞。早くもその頭角を現していました。
芸術家としての道を決定づけたのは、高校時代の出会いでした。当時東京藝術大学の大学院生だった版画家・中林忠良が美術の時間講師として教鞭を取るようになり、この出会いが有元を本格的な芸術の道へと導くきっかけとなったのです。
その後、有元は東京藝術大学を目指しますが、すぐには合格できませんでした。しかし、4年にも及ぶ浪人期間は、決して無駄ではありませんでした。この時期に厳格な石膏デッサンを会得し、さらには「デッサンとは何か、本物の美とは何か」という根本的な問題について深く思索を重ねたのです。
早世の天才画家とも評されており、1985年、肝臓癌で死去。墓は長久院墓地(東京都台東区谷中6-2-16)にあります。

画家としての転換点
1969年、東京藝術大学美術学部デザイン科への入学を果たした有元の前に、さらなる転機が訪れます。在学中に経験したヨーロッパ旅行、特にイタリアでの体験は、彼の芸術観を根底から変えることとなりました。
イタリアで出会ったフレスコ画に心を奪われた有元は、その神秘的な魅力に新たな可能性を見出します。帰国後、フレスコ画の持つ独特の質感を追求するため、岩絵具*や顔料を用いた新しい表現技法の開発に没頭していきました。
その努力は実を結び、1973年の卒業制作「私にとってのピエロ・デラ・フランチェスカ」は大学に買い上げられる栄誉に輝きます。その後も、1978年の「花降る日」での安井賞特別賞、1981年の「室内楽」での安井賞受賞と、その評価は着実に高まっていきました。
では、有元利夫はどのようにして、他の誰にも真似のできない独自の表現世界を築き上げていったのでしょうか。
※岩絵具:天然の鉱石を細かく砕いて作られる顔料。日本画の伝統的な画材で、粒子の大きさにより「荒目」「中目」「細目」などに分けられる。通常は膠(にかわ)などの接着剤と混ぜて使用する。

出典:Wikipedia
有元利夫の作品の魅力や特徴

独自の表現技法
有元利夫の作品に出会った人々は、その独特の世界観に心を奪われます。それは、フレスコ画と日本の仏画という、一見かけ離れた二つの技法を見事に融合させた独創的な表現によるものでした。
フレスコ画から得た着想に、岩絵具や金泥という日本の伝統的な画材を組み合わせることで、有元は新たな油彩技法を確立します。さらに特筆すべきは、多くの画家が避けようとする「風化」という現象さえも、作品の一部として取り入れた点です。剥落や虫食いの跡を意図的に施すという斬新な手法は、当時の常識を覆すものでした。
興味深いことに、有元がフレスコ画に感動した理由は、それが日本の平家納経や仏画と共通点を持っていたからでした。「東西の偉大な宗教画の共通点は、キリストや仏といった偉大なものを大きく描く、姿かたちはどの時代も同じよう」という気づきが、有元の独自の表現技法を生み出すきっかけとなったのです。
代表的な作品群
そんな有元利夫の独創性が遺憾なく発揮された代表作の一つが「花降る日」です。花びらが舞う中で佇む女性の後ろ姿を描いたこの作品は、1978年に安井賞特別賞を受賞。見る者を幻想的な世界へと誘う、有元芸術の真髄といえる作品です。
また、1980年に発表された「室内楽」も、有元の代表作として高い評価を受けています。中央に描かれたふくよかな女性の姿を通じて、音楽のリズムを視覚的に表現しようと試みたこの作品は、安井賞を受賞。有元の芸術観が結実した傑作として、今なお多くの人々の心を捉えています。
版画作品においても、有元は独自の世界を築き上げました。特に注目すべきは、一般的な作家が100部以上制作するところを、有元の版画は100部以内の限定制作が多いという点です。「赤い部屋」は50部限定で制作され、「占いの部屋」は81部限定のリトグラフ作品として知られています。

モチーフと世界観
有元利夫の作品世界で特徴的なのは、一貫して人物を描き続けていることです。1973年の卒業制作から1984年の最晩年の作品まで、時には人形や犬なども描きましたが、その主題は常に人物画でした。
描かれる人物たちは、どこか神秘的な雰囲気を漂わせています。無表情の顔で古代ヨーロッパを思わせる衣装を身にまとい、まるで童話の世界に迷い込んだかのような不思議な魅力を放っています。花や音楽、手品、花火といったモチーフも多く用いられ、素朴さと幻想性が見事に調和した独自の世界観を作り出しているのです。
バロック音楽*との出会いも、有元の作品世界に大きな影響を与えました。大学3年になる直前、友人の音楽学部の学生からリコーダーを教わったことをきっかけに、バロック音楽に強く惹かれていったといいます。この音楽との出会いは、後の作品における独特のリズムや構成にも影響を与えることとなりました。
※バロック音楽:17世紀初頭から18世紀半ばまでのヨーロッパ音楽様式。装飾的で情緒豊かな表現、対位法の発展、通奏低音の使用などが特徴。バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディなどの作曲家が代表的。
有元利夫の作品の買取相場・実績
※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。
遊戯

冬:「Les QUATRES SAISONS」4葉より

有元利夫の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。
有元利夫の作品を高値で売却するポイント

有元利夫の鑑定機関・鑑定人
来歴や付帯品・保証書
来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。
保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。
贋作について
1980-1983年に制作された版画6作品については、奈良県の工房によって偽作が製作され、市場に流通したことが判明しています。その作品については鑑定機関「有元利夫作品鑑定委員会」にて鑑定登録をおこなっています。
1.赤い部屋 リトグラフ 1980年制作
2.蒼い風 リトグラフ 1981年制作
3.MAGIC 占いの部屋 リトグラフ 1981年制作
4.MAGIC 遊戯の部屋 リトグラフ 1981年制作
5.MAGIC 雲の部屋 リトグラフ 1981年制作
6.遊戯 リトグラフ 1983年制作
お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。
油彩画(額)
状態を良好に保つ為の保管方法
油絵は主に布を張ったキャンバスと言われるものに描かれています。他にも板に直接描かれた作品もあります。油絵の具は乾燥に弱く、色によってはヒビ割れ目立つ作品が見受けられます。また、湿気によりカビなどが付着しやすく、カビが根深い場合は修復困難となってしまいます。高温多湿を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。
修復方法
油彩画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります。
版画
共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)
版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。
主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。
リトグラフ
石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。
木版画
板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。
有元利夫についての補足情報
展覧会と美術館での評価

有元利夫の芸術性は、その受賞歴からも明らかです。画壇からの評価は着実に高まり、わずか10年の画業の中で、以下のような重要な賞を受賞しています:
・1978年:安井賞特別賞
・1981年:安井賞
・1983年:第2回美術文化振興協会賞
制作された作品は決して多くありません。生涯に残した作品はタブロー(絵画)371点、版画作品130点のみです。これらの作品はいずれも独自の芸術性と深い静寂感を湛えており、美術館や個人コレクターから高い評価を受け、希少性の高いものとして現代美術史に位置づけられています。
展覧会活動も精力的に行われました。1975年に初個展を開催して以降、各地で展示会や個展を継続的に開催。没後も企画展や回顧展が定期的に開催され、その芸術性は時代を超えて評価され続けています。
近年の主な展覧会:
・2024年:THE MIRROR「春の音色を聴く 〜有元利夫 in 松川ボックス〜」
・2024年:大阪中之島美術館「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」
これらの展覧会活動を通じて、有元芸術の価値は現代においても着実に高まっています。
まとめ
わずか10年という短い活動期間ながら、日本の洋画界に新たな地平を切り開いた有元利夫。フレスコ画と日本の伝統を融合させた独自の表現技法と、幻想的な世界観は、今なお多くの人々を魅了し続けています。
バロック音楽を愛し、「見る人に物語を紡がせる絵を描きたい」という思いを抱き続けた有元利夫。その作品は、時代を超えて私たちの心に深い感動を与え続けているのです。
近年、その作品の価値は再評価され、美術品市場での需要も高まっています。作品をお持ちの方は、その真価を見極めるためにも、まずは専門家による査定をお勧めします。
当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。有元利夫の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。
また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。