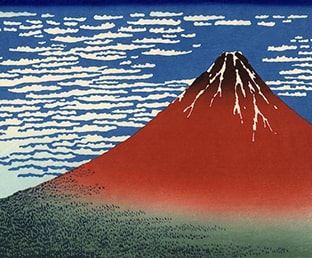はじめに
「近代の左甚五郎」と称された高村光雲(たかむら こううん)。上野公園の「西郷隆盛像」や皇居前広場の「楠公像」など、その名を聞いて思い浮かぶ作品は多いのではないでしょうか。
高村光雲は明治から大正時代にかけて活躍した彫刻家・仏師(※)です。西洋の写実主義と伝統的な日本の木彫技術を見事に融合させ、独自の芸術世界を構築しました。廃仏毀釈の波や象牙彫刻の流行という逆風の中でも、光雲は木彫に対する情熱を失わず、日本の彫刻界に大きな足跡を残したのです。
今回は、そんな高村光雲の生涯と作品の魅力をご紹介します。作品の価値や特徴についても解説しておりますので、光雲作品をお持ちの方、売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。
※仏師:彫刻家の中でも特に仏像を専門に制作する職人のこと。

高村光雲とは?
江戸から明治へ、変革期を生きた彫刻家
高村光雲は1852年、江戸下谷(現在の東京都台東区)で誕生しました。本名は中島幸吉、幼名は光蔵と呼ばれていました。
彼が彫刻の道を歩み始めたのは11歳の時。近所の床屋の紹介で仏師・高村東雲に弟子入りしたのが始まりでした。その後、兵役を回避するため1874年に東雲の姉・エツの養子となり、高村姓を名乗るようになりました。これが「高村光雲」誕生の瞬間です。東雲のもとで仏像彫刻の技術を熱心に学んだ光雲は、若くしてその才能を認められる腕前となったのです。
廃仏毀釈と象牙彫刻の流行に抗した木彫の守護者
光雲が独立して仏師として歩み始めた時期は、日本社会が大きく変わろうとしていた明治維新の激動期でした。廃仏毀釈(※)の風潮が高まり、仏教に関連する仕事は激減。さらに当時は輸出品として象牙彫刻が人気を集め、木彫の仕事も減少していたため、彼の生活は次第に困窮していきました。
その時代、「象牙にあらざれば彫刻に非ず」と言われるほど象牙彫刻が隆盛をむかえていました。多くの仏師が木彫から象牙彫刻へと転向する中、光雲だけは頑なに木彫にこだわり続けたのです。
このような姿勢の背景には、師匠・東雲から受け継いだ言葉があったと考えられます。「いやしくも仏師たるものが、自作を持って道具屋の店に売りに行く位なら、焼き芋でも焼いていろ、団子でもこねていろ」という教えが、光雲の心に深く刻まれていたのでしょう。
時代の逆風にも負けず、光雲は「木で彫れるものなら何でも彫る」という信念を貫き、西洋美術の要素を積極的に学びながら木彫の道を進み続けました。彼は衰退の危機にあった木彫に写実表現を取り入れることで新たな可能性を開き、江戸時代からの木彫技術を近代に継承する重要な役割を果たしたのです。
※廃仏毀釈:明治初期に起こった仏教排斥運動。仏像や仏具などが破壊された。
世界に認められた日本の彫刻家

光雲の名が世に知れ渡るきっかけとなったのは、1877年に開催された第1回内国勧業博覧会でした。師匠・東雲の代理として出品した「白衣観音」が最高位の龍紋賞を獲得し、彫刻家としての評価が一気に高まりました。
その後も様々な作品を発表して評価を集めた光雲は、1886年に東京彫工会を創設。翌年からは皇居建設に伴う装飾部分の制作を担当するなど、活躍の場を着実に広げていきました。
1889年には制作した「矮鶏置物」が明治天皇の目に留まり、御買い上げとなる栄誉に浴します。同年、美術教育に尽力していた岡倉天心の招きにより、東京美術学校(現・東京藝術大学)の教師として迎えられました。
翌1890年には彫刻科教授に任命され、同時に帝室技芸員(※)という名誉ある地位も得ました。教育者としても熱心に後進を育成し、山崎朝雲、米原雲海、平櫛田中など、後の日本彫刻界を担う多くの優れた彫刻家を輩出しています。
光雲の評価は日本国内にとどまらず、国際的にも高い評価を受けました。1893年にシカゴで開催された万国博覧会には「老猿」を出品して優等賞を獲得。1900年にはパリ万国博覧会にも「山霊訶護」を出品し、世界的にも日本を代表する彫刻家としての地位を確立していったのです。
※帝室技芸員:明治時代に設けられた制度で、美術や工芸の分野で優れた技術を持つ人物に与えられた称号。現在の人間国宝に相当する。

高村光雲の作品の魅力や特徴
写生に基づく精緻な表現技法
高村光雲の作品が持つ最大の特徴は、その卓越した写実的表現にあります。当時の木彫の世界では写実性はさほど重視されていませんでしたが、光雲は西洋美術の要素を積極的に取り入れ、写実主義に基づいた新たな木彫技術を確立しました。
彼は画家のように対象を綿密に観察し、写生を重ねることで、作品に驚くほどの生命感を吹き込むことに成功しました。制作過程で描いた数多くのスケッチが現在も残されており、そこからは彼の鋭い観察眼を窺い知ることができます。
特に注目すべきは、動物をモチーフにした作品を制作する際の徹底した姿勢です。光雲は必ず実際の動物をモデルとして飼育し、その動きや表情を細部まで観察してから彫刻に取り掛かりました。このような徹底した姿勢があったからこそ、彼の作品には生き生きとした表情が宿っているのです。
光雲の作品は、小さなものであっても目の周りの皺や口元の細部に至るまで緻密に表現されており、衣服の質感や柔らかさまでも感じさせる技術を持っていました。動物を題材にした作品では毛並みの流れや皮膚の質感が見事に表現され、まるで今にも動き出しそうな迫力を感じさせます。
代表作とその魅力
高村光雲は小さな置物から大型の公共彫刻まで、多岐にわたる作品を残しました。その中でも特に知られる代表作をご紹介します。
・老猿(1893年)
シカゴ万博で優等賞を獲得し、後に国の重要文化財に指定された名作。岩の上で片膝を立てて座り、鷲の羽を握りしめ遠くを見つめる姿は、直前まで繰り広げられた激しい戦いを想像させます。制作直前に16歳の愛娘を亡くした光雲の悲しみが、作品の深い精神性と迫力に反映されています。
・矮鶏置物(1889年)
繊細な羽毛や鶏冠の表現に至るまで写実の真髄を極めた傑作。明治天皇の目に留まり買い上げられるという栄誉に浴しました。当初はパリ万博への出品を予定していましたが、理想的なモデルを探す苦労の末、美術協会の展覧会を経て天皇の目に留まるという幸運に恵まれました。
・西郷隆盛像(1897年)
上野公園に建立された銅像で、「上野の西郷さん」という愛称で今日も親しまれています。弟子たちとの共同制作で、日本で初めて造船技術を応用した鋳造方法を採用し、継ぎ目のない完成度の高い像に仕上げられています。
・楠公像(1893年)
皇居前広場に立つ、鎌倉時代の武将・楠木正成を描いた銅像。東京三大銅像の一つとして数えられ、宮内庁への献納品として光雲が製作主任を務めました。光雲は主に顔部分を担当し、複数の彫刻家による分業制で制作されました。
・仁王像(1919年)
長野県の善光寺仁王門に安置されている、弟子の米原雲海との共同制作による巨大木彫。迫力ある表情と姿勢が特徴的で、100年以上経った今でも自立している構造の精巧さも驚きです。

このように光雲の作品は、小さな動物彫刻から公共彫刻、仏像まで幅広いジャンルにわたります。いずれの作品も写実に基づく精緻な表現と、対象の内面までも表現する深い洞察力が共通しています。東京を訪れた際には、上野公園の「西郷隆盛像」や皇居前広場の「楠公像」を是非一度じっくりとご覧になってみてはいかがでしょうか。
高村光雲作品の買取相場・実績
※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。
大聖像

彫刻

観音菩薩像

高村光雲の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。
高村光雲の作品を高値で売却するポイント

高村光雲の鑑定機関・鑑定人
- 高村達
高村光雲・高村光太郎の鑑定人。
来歴や付帯品・保証書
来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。
保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。
贋作について
ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。
落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。
木彫
共箱(ともばこ)
近代美術の工芸作品には作品を収納する木の箱が付帯しています。蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は証明書の役割をしているので一緒に保管しましょう。
共箱が付帯しない作品
共箱の定義として共箱が確認されている作品は現在〜江戸時代までの作品が多いようです。それ以前の作品には無い場合も有り、作家より骨董品としての評価になる事があります。作品そのものの魅力や技巧、歴史等が考慮された上での評価される場合があります。
サイン
国内の工芸品にはほとんどの作品に作家名が記されていることがあります。代々続くような工芸作家はサインにより何代目の作品か等特定できることがあります。
ブロンズ
状態を良好に保つ為の保管方法
ブロンズは主に銅で制作され、劣化しにくいことから街のいたるとこにモニュメントとしてブロンズ製の銅像などが存在します。お手入れとしては水を含ませた布で優しく拭うように埃を取り除きましょう。深緑色に変化することもありますが、味わいとして楽しめる一方で、ムラや痛みには気をつけたほうがいいでしょう。
真贋
元々鋳造技法で制作されている為、複製しやすく贋作も多く見受けられます。ブロンズ作品は底や背面に作家のサインの記載がある事が多く、確認してみましょう。
高村光雲についての補足情報
高村光雲の人柄と創作姿勢
東京美術学校の教師に招かれた際、光雲は最初「文字も学問も身についていない私が教える立場になるなど考えられない」と断りましたが、岡倉天心の熱意に応える形で教壇に立つことを承諾しました。このエピソードからも、光雲の謙虚さと真摯な人柄が伝わってきます。
芸術家としての光雲は、常に写生を重視し、西洋美術から学んだ写実性と日本の伝統技法を融合させた新しい表現を追求し続けました。この姿勢こそが、彼が「近代の左甚五郎」と称される名匠となった所以でしょう。
光雲を支えた家族と弟子たち
高村光雲の家族もまた芸術の世界で活躍しました。長男の光太郎は彫刻家・画家としての才能だけでなく、詩人としても名を残し、三男の豊周は彫金の世界で成功を収めました。光雲の周囲には自然と芸術的才能が花開く環境が整っていたのでしょう。
光雲は山崎朝雲、米原雲海、平櫛田中など多くの弟子を育て、彼らはいずれも近代日本彫刻界を代表する彫刻家として大成しました。
現代に残る高村光雲の遺産
現代においても、高村光雲の作品は東京国立博物館の「老猿」や東京芸術大学の「聖徳太子坐像」など、多くの美術館・博物館に収蔵されています。上野公園の「西郷隆盛像」や皇居前広場の「楠公像」は今なお多くの人々に親しまれており、光雲の芸術的遺産は私たちの日常風景の中にも息づいています。
まとめ
西洋の写実主義と日本の伝統技法を融合させ、廃仏毀釈の波や象牙彫刻の流行という逆風の中でも木彫への情熱を失わなかった高村光雲。彼の作品は、美術館での展示はもちろん、上野公園の「西郷隆盛像」や皇居前広場の「楠公像」など、今なお私たちの身近な場所で、その芸術的価値を伝え続けています。
「老猿」のような緻密な動物彫刻から仏像、公共彫刻まで、幅広いジャンルで才能を発揮した光雲の作品は、美術品としての価値と芸術的・歴史的価値の両面で高い評価を得ています。
当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。高村光雲の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。
また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。